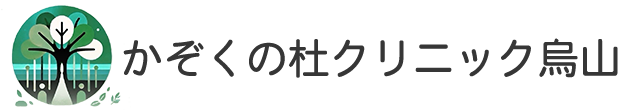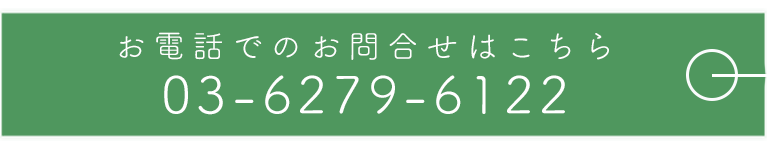一般精神科外来
一般精神科外来
一般精神科外来について
一般精神科外来では、心の健康に関するさまざまな症状やお悩みに対応しています。
現代のストレス社会において、不安、抑うつ、睡眠障害、パニック障害など、心の不調を抱える方は増加しています。
精神疾患は、誰にでも起こり得る身近な病です。もし、ご本人やご家族が患ったとしても、それは決して特別なことではありません。
本来、人間には困難な状況にもうまく適応して、自分らしい生き方を見出す力を持っているはずなのです。しかし、おひとりで対処するには大き過ぎる、現代社会の様々なストレス要因(環境や人間関係など)により、その力が十分に機能し難くなってしまうことがあります。
当院では、患者さま一人ひとりの症状やお悩みに丁寧に寄り添い、適切な診断と治療を行いますので、おひとりで解決されようとせず、是非一度ご相談ください。
治療について
治療方法は、主治医との面接や薬物療法、カウンセリングなどを中心に、患者さまの状態にあわせて最適な方法をご提案いたします。
心の病気は決して特別なものではなく、適切な治療を受けることで回復が期待できます。
「もしかして…」と感じたら、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
当院は、安心して通院いただける環境を整えております。
疾患・症状について
うつ病
うつ病は、脳のエネルギーが不足している状態です。
それによって、憂うつな気分やさまざまな意欲(食欲、睡眠欲、性欲など)の低下といった心理的症状が続くだけでなく、さまざまな身体的な自覚症状を伴うことも珍しくありません。
エネルギーの欠乏により、脳というシステム全体のトラブルが生じてしまっている状態と考えることができます。
一日中気分が落ち込んでいる、何をするにもおっくう、漠然とした不安感が続くなどの精神的な症状や、眠れない、食欲がない、体がだるい、疲れやすいなどの身体的な症状が一定期間続く場合、うつ病が疑われます。
日常生活の中で憂うつになることは誰しもが経験しますが、うつ病の場合には気分が落ち込んだ原因が解決しても気分が回復しません。
まずは休養が大切ですが、ストレスを軽減させるような環境調整や抗うつ薬などのお薬での治療を組み合わせて、症状を改善していきます。
双極性感情障害
無気力で気分が落ち込むうつ状態と、極端に調子が良くなり活動的になる時期が交互に訪れる場合、双極性感情障害(躁うつ病)が疑われます。
このような気分の上がり下がりが激しい状態は、本人にとって非常に辛く、社会的な活動にも支障をきたします。
躁状態では、エネルギーにあふれ、気分が高揚し、睡眠が十分でなくても元気になった気がすることがあります。そのため、患者さん自身は病気であると認識せず、普段とは異なる言動を取ることで周囲に心配されることが多いです。
また、うつ状態に陥り、気分の落ち込みや疲れやすさなどを自覚してから医療機関に受診することが一般的で、うつ病と診断され、治療を受けることもあります。
双極性感情障害は、うつ病とは治療法が異なります。
適切な治療により気分の波を抑えることが可能ですが、まずは正しい診断を受けることが非常に重要です。
統合失調症
考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く、精神疾患です。
統合失調症は誰しもが発症する可能性があり、特に思春期を含む若年層で発症しやすいとされています。
その原因は十分に解明されていませんが、脳のさまざまな機能が複雑に絡んでいます。
主な症状として、陽性症状、陰性症状、認知機能障害、不安・抑うつといった症状が現れます。
再発しやすい病気ですが、適切な治療を受けることで回復することが可能です。
統合失調症は、早期発見と早期治療がとても重要です。
適応障害
ストレスが強い状況に直面した際に、そのストレスに適切に適応できず、心身にさまざまな不調が現れる状態を指します。
日常生活や仕事、人間関係などの変化に対して過度に反応し、通常の範囲を超えた心理的、身体的な症状が現れることが特徴です。
職場での過度の負担、家庭内の問題、転職や引越しなどの生活の大きな変化がきっかけとなり、気分の落ち込み、過剰な不安、眠れない、食欲がなくなる、身体がだるくなるなどの症状が現れることがあります。
これらの症状は通常、ストレスの原因が解消されることで改善することが多いですが、長期間続いたり、症状がひどくなる前に治療が必要です。
適応障害は、特定の精神疾患に分類されるものの、症状がうつ病や不安障害に似ていることがあります。
カウンセリングや認知行動療法を通じて、ストレス対処法を学ぶことや、必要に応じて薬物療法を行うことで症状を改善していきます。
不眠症
夜なかなか寝つけない、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまう、眠りが浅く十分眠った感じがしないなどの症状が続き、よく眠れないため日中の眠気、注意力の散漫、体がだるいといった不調があらわれることがあります。
日本では、約5人に1人が不眠の症状に悩んでいると言われています。
不眠症は、小児期や青年期には少ないですが、20~30歳代から増え始め、加齢とともに増加し中年、老年と急激に増加します。
不眠の原因には、ストレスや生活リズムの乱れ、体の病気、加齢などさまざまなものがあります。
眠れない日が続くと、心や体に負担がかかってしまうため、早めに対策をすることが大切です。
不安障害
「過剰な不安や恐怖」によって、日常生活に支障が出てしまう状態のことです。
本来、人が感じる「不安」や「恐怖」は危険を回避するために備わっている重要な機能のひとつです。
このような不安や恐怖は、誰にでも起こる自然な感情ですが、不安障害では、こうした信号が過剰に働いてしまうため、必要以上に強い不安や恐怖を感じ、日常生活に大きな支障が出てしまうことがあります。
人前での発表や意見を述べる場面など、誰でも多少の緊張や不安を感じる状況において、不安障害の方は、通常よりもはるかに強い不安を覚え、その結果、毎日の生活や仕事にまで影響が及んでしまうことがあります。
「不安障害」は「不安神経症」とも呼ばれ、強い不安や恐怖を過剰に感じることで、社会生活や人間関係にまで支障をきたしてしまう病気の総称です。
気になる症状がある場合には、無理をせず、できるだけ早くご相談いただくことが大切です。
早期に適切な治療を始めることで、症状の悪化を防ぎ、より良い日常生活を取り戻すことができます。
月経前症候群
月経(生理)が始まる3~10日ほど前から、身体や心にさまざまな症状が現れる病気を月経前症候群(PMS)と呼びます。
これらの症状は、月経の開始とともに自然に弱まったり、なくなったりするのが特徴です。
月経のある女性のおよそ70~80%は、月経前に何らかの不快な症状を感じるといわれていますが、PMSはその中でも症状の程度が強い状態を指します。
症状の現れ方は個人差があり、軽いものから、日常生活や社会生活に支障をきたすほど重いものまでさまざまです。
身体に起きる症状としては、むくみ、便秘、腹痛、頭痛、肩こり、乳房の張りといった代表的なもののほか、不眠、強い疲労感、記憶力の低下など、報告されている症状は200~300種類にも及ぶといわれています。
また、精神的な症状としては、イライラ感、憂うつ感、不安感などが挙げられ、日常生活の中で精神的な負担を大きく感じる方も少なくありません。
PMSの症状をやわらげるには、PMSについて正しく理解し、自分の症状を把握することが重要です。
患者さまの症状に合わせて、医師と治療方針を決めていきます。
自律神経失調症
自律神経失調症とは、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが崩れることによって、心身にさまざまな不調が現れる状態です。
自律神経は、呼吸・血圧・消化・体温調整など、生命活動を無意識にコントロールしている大切な神経です。
本来、交感神経と副交感神経がバランスよく働くことで体の調子を保っていますが、日々のストレス、生活リズムの乱れ、過労、不規則な睡眠などが影響し、このバランスが崩れることで、体内のコントロールがうまくいかず、さまざまな不調が引き起こされます。
主に動悸、発汗、めまい、頭痛、胃痛、腹痛、下痢、吐き気、ふるえ、筋肉痛、喉のつまり感、息切れ、食欲不振、全身倦怠感など、複数の身体症状がみられます。
これらの症状について、検査をしても臓器や器官に明らかな異常が認められない場合に、「自律神経失調症」と診断されることがあります。
治療法としては、生活習慣の見直しや、必要に応じて薬物療法、カウンセリングを行い、自律神経のバランスを整えることを目指します。
症状が続いている場合や、日常生活に支障が出ている場合には、無理をせず、できるだけ早めにご相談ください。
身体表現性障害
強い痛みや吐き気、しびれなどの身体的な症状を訴えているにもかかわらず、検査結果や医学的な所見では特別な異常が認められない状態が長期間にわたって続く病気です。
症状は体のさまざまな部位に現れ、時間とともに変化することもあります。
中には、体に力が入らなくなったり、けいれん発作のような症状を経験される方もいらっしゃいます。
このような症状に対して、身体的な原因が見つからないことを受け入れがたく、いくつもの医療機関を受診されたうえで、ようやく精神科受診に至る方も少なくありません。
また、多くの患者様は、こうした身体症状により仕事や学校、家庭生活などに支障をきたしているのが現状です。症状は「気のせい」では決してなく、患者様にとって非常にリアルでつらいものです。
そのため、単に身体だけを診るのではなく、心のケアも含めた総合的なサポートが大切です。
治療については、ストレスマネジメント、薬物療法、カウンセリングなどを必要に応じて組み合わせながら進めていきます。
認知症
正常に発達した脳の働きが、何らかの原因で低下し、記憶力・判断力・理解力などに障害が出て、日常生活に支障をきたす状態をいいます。
加齢に伴う、もの忘れと違い、認知症では「体験そのもの」を忘れてしまうのが特徴です。
例えば、もの忘れであれば「朝ごはんに何を食べたか忘れる」ことが多いですが、認知症では「朝ごはんを食べたこと自体を覚えていない」という状態になります。
認知症を引き起こす原因となる病気はさまざまありますが、代表的なものに「アルツハイマー型認知症」や「脳血管性認知症」があります。これらは、脳の神経細胞が死んでしまったり、脳にダメージを受けることで起こります。
認知症は、完全に予防することは難しく、症状が進行するものですが、早期発見・早期対応によって進行を遅らせることができる場合があります。
本人にとってもご家族にとっても、早めにサポート体制を整えることが大切です。